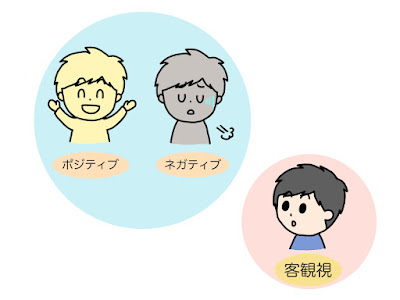気沈丹田を意識する利点は何だろう?(Part.2)

貯蔵した気は、軽快に動くための動力源 太極拳の攻防の動きは、相手と接している前提のものであり、1人で套路をやっていても、それは相手との攻防をシミュレーションしているに過ぎない。本来、相手と対峙するとき、興奮状態にあってはならない。興奮状態にある人は、全身が強張って力がみなぎり、繊細な感覚が鈍る。相手と自分の状態を冷静に察する事ができない。 丹田に気を下ろす意識を持つことで、心身の安定感が保たれ、頭に血が上るような、のぼせた状態は避けられる。相手との攻防など一切意識せず、健康法として套路のみを励行する人も、興奮状態で動けば気持ちよく運動できない。興奮と緊張で硬い動きになれば、血圧も上がり、筋肉疲労も溜まり、体内の老廃物を上手く流せない。 気の概念からすると、 臍下丹田あたりは気が満ちている場所(気海) であり、スムーズに動く為には、満ちた気をそこから全身に運ぶイメージを持つと良い。そうすると筋肉に無駄な力が入りにくく、心が 落ち着く。 さらに太極拳の分野では、気を「旗振り役」とみなす事がある。温存している人体内の気を、意識を集中しながら、必要に応じて人体の中で巡らす。そうする事で、気はヒトの活動を促す為の「旗振り役」となり、太極拳の攻防において勁の誘導役となる。ちなみに太極拳に関連する昔の理論書の中には、「氣為旗(気は旗をなす)」という味わい深い言い回しがある。 太極拳に関わる昔々の理論書をいろいろ読んでいくと、おもしろい表現によく出くわす。気が沸き立つ…とか、気が鼓蕩する…等々。 十三勢行功歌という、武術の鍛錬の要領についてうたった古くからの歌訣がある。この歌訣は、現在、我々太極拳愛好家の学びとなるバイブルの中の1つでもある。 十三勢行功歌の中に、 「刻刻留心在腰間 腹内鬆静気騰然」 というフレーズがある。大雑把ではあるが自分なりに意訳してみると、大体こんな感じ。「随時、腰のあたりに心を留めて、 腹内を力ませずに柔軟にし(鬆静)、腹内にある気が沸き巡るようになる(氣騰然)」。 ただし、 太極拳の攻防において、気はいったん背骨あたりに収める…という考え方がある。むやみに沸き立たせて気を方々へ散らしては勁を誘導できないわけで、攻防の技に気を活用するには、浪費せずに大切に収めて上手く運行させる必要があるだろう。太極拳初心者の方がこのイメージを体現できるか?と言われれば、で...